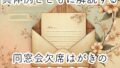猫の疥癬症(かいせんしょう)は、ヒゼンダニというダニが皮膚に寄生することで発症し、強いかゆみや皮膚の炎症を引き起こします。
適切な予防と治療を行うことで、愛猫の健康を守ることができます。
疥癬症とは?

疥癬症は、ヒゼンダニが猫の皮膚に寄生し、皮膚の角質層に穴を掘って産卵することで発症します。
これにより、猫は強いかゆみや皮膚の炎症を感じるのです。場合によっては食欲不振や体重減少を引き起こすこともあります。
主な症状として、以下のものが挙げられます。
- 激しいかゆみ
- 皮膚の赤みや発疹
- フケの増加
- 脱毛
- 皮膚の硬化や厚み
- 皮膚のただれやかさぶた形成
- かゆみによるストレスの増加
これらの症状は、耳や顔から始まり、全身に広がることがあります。とくに若い猫や免疫力が低下している猫では、症状が重くなる傾向があるので要注意です。
また、感染が進行すると皮膚の損傷がひどくなり、細菌感染を併発するリスクも高まります。その結果、膿皮症などの二次感染を引き起こし、治療が長期化することもあり得るのです。
ヒゼンダニは目に見えないほど小さな寄生虫であり、顕微鏡を使わなければ確認できません。そのため、肉眼で確認することは難しく、猫の行動や皮膚の異変に注意を払うことが重要です。
とくに、猫が異常に体をこすりつけたり、掻きむしる様子が見られる場合は、早めに動物病院を受診することが推奨されます。
疥癬症の予防方法

疥癬症を予防するためには、以下のポイントに注意することが重要です。
1. 感染源との接触を避ける
疥癬症は、感染した猫との直接的な接触や、感染猫が使用したタオルやブラシなどを共有することで広がります。そのため、外出時には野良猫との接触を避け、室内飼いを徹底しましょう。
また、新しく猫を迎える際には、他の猫と接触させる前に健康状態を確認することが大切です。
さらに、ペットホテルや動物病院に預ける際も、清潔な環境が整っているかを確認することが予防に繋がります。
2. 飼育環境の清潔維持
日常的に猫の生活環境を清潔に保つことで、ダニの繁殖を防ぐことができます。
猫の寝床やおもちゃ、トイレなどを定期的に洗浄・消毒し、室内の湿度管理を行いましょう。
ヒゼンダニは高温と乾燥に弱いため、50℃以上のお湯で10分以上の洗浄が効果的です。また、部屋の換気をこまめに行い、湿度が高くならないように除湿機を有効に活用しましょう。
加えて、掃除機を使ってカーペットやソファなどの隙間に潜むダニを除去することも大切です。
3. 定期的な健康チェック
定期的に猫の皮膚や被毛の状態をチェックし、異常がないか確認しましょう。早期発見・早期治療が重症化を防ぐ鍵となります。
とくに、かゆがる様子や皮膚の変化に気付いた場合は、早めに動物病院を受診してください。
さらに、定期的に動物病院での健康診断を受けることで、より早く異変を察知することができます。獣医師による専門的な診察を定期的に受けることは、皮膚疾患だけでなく他の病気の早期発見にも役立ちます。
また、猫のストレスが免疫力の低下を引き起こすため、快適な環境を整えることも重要です。
疥癬症の治療方法

万が一、愛猫が疥癬症に感染してしまった場合、以下の治療法が一般的です。
1. 駆虫薬の投与
ヒゼンダニを駆除するための薬を使用します。主に以下の薬剤が用いられます。
- セラメクチン:皮膚に滴下するスポットオンタイプの薬剤で、2週間ごとに3回の投与が推奨されています。
- イベルメクチン:内服薬や注射として使用され、週に1回の投与が基本です。
- モキシデクチン:一部の駆虫薬に含まれ、長期間効果が持続するタイプの薬剤です。
- アミトラズ:外用薬として使用されることがあり、重度の感染に対処するために使われることがあります。
これらの薬剤はダニの卵には効果がないため、複数回の投与が必要となります。
治療期間中は獣医師の指示に従い、投薬を継続してください。症状が改善したように見えても、ダニが完全に除去されるまで治療を続けることが重要です。
2. 環境の消毒
感染猫が使用していた寝具やおもちゃ、ブラシなどは、熱湯消毒や洗浄を行いましょう。ヒゼンダニは環境中でも数日間生存するため、再感染を防ぐためにも徹底した清掃が重要です。
- 寝具やタオル類は50℃以上の熱湯で洗浄し、天日干しをする。
- 掃除機を使い、カーペットやソファなど猫がよくいる場所を清掃する。
- 家具や床も消毒液を使用して拭き掃除を行う。
環境の清掃を継続的に行い、ダニの再繁殖を防ぐことが大切です。
3. 他のペットや人間への注意
疥癬症は他の動物や人間にも感染する可能性があります。感染した猫は他のペットと隔離し、接触を避けるようにしましょう。
また、猫のお世話をする際には手袋を着用し、接触後は手洗いを徹底してください。
- 他のペットにも症状が現れていないか定期的にチェックする。
- 人間にも感染する可能性があるため、かゆみや発疹が出た場合は皮膚科を受診する。
- 猫を隔離するスペースを確保し、治療期間中は他の動物との接触を最小限にする。
症状が落ち着いても再発の可能性があるため、定期的な健康診断を受けることをおすすめします。
まとめ

猫の疥癬症は、適切な予防と早期の治療によって、重症化を防ぐことができます。日常的な健康チェックと清潔な環境の維持を心掛け、愛猫の健康を守りましょう。
もし異常を感じた場合は、早めに獣医師に相談することが大切です。
愛猫の健康を守るために、定期的な健康チェックと清潔な環境の維持を心掛けましょう。異常を感じたら、早めに獣医師に相談してください。